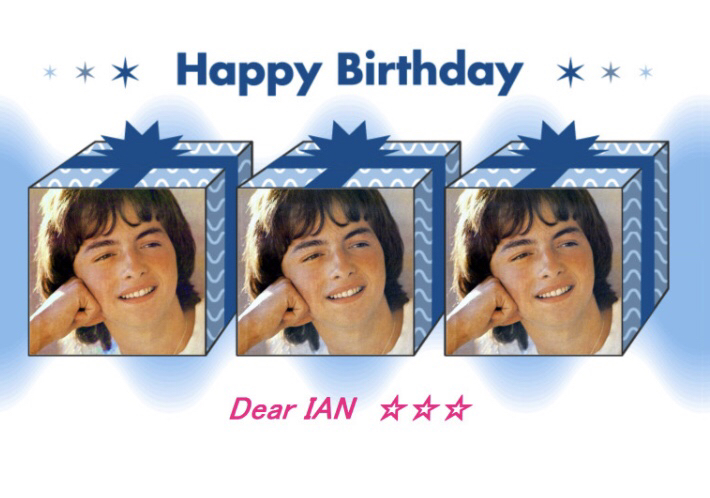2019.8.19
新旧お宝アルバム #154
『Guitar Town』Steve Earle (MCA, 1986)
長いことかけて日本を横断していた台風10号も去り、また猛暑の毎日、皆さんいい音楽で暑さをしのいでますか?この週末はサマソニで大いに盛り上がった方も多かったのでは。そしてこういう暑いときこそ、熱い音楽を聴いて大いに盛り上がって暑さを吹き飛ばしたいですね。
さて今週の「新旧お宝アルバム!」は80年代に戻ってみます。当時ソングライターとしての実績を踏まえて鮮烈にデビュー、その時その時の社会情勢や自らの心情を吐露するアルバムを多く世に出す一方、結婚と離婚、ドラッグやアルコール依存症による健康問題、不法銃器所持で拘留されるなど波瀾万丈の人生を送りながら、今も力強く自分の歌を作り歌い続けている80年代ネオ・カントリーの旗手、そして今に脈々と続くオルタナ・カントリー・ロックの先駆者、スティーヴ・アールの鮮烈なデビュー盤『Guitar Town』(1986)をご紹介します。
アメリカーナ・ロックや、オルタナ・カントリー・ロックのアーティストを既に多く聴き親しんでいる洋楽ファンの間では、スティーヴ・アールという名前は既に説明する必要のないくらい、こうしたジャンルの先駆者として、そしてシーンを常にリードするアーティストとして知れ渡っていますが、こうしたジャンルに親しんでいない洋楽ファンには、ひょっとしてあまり聴き覚えのない名前かもしれません。
テキサス州はサン・アントニオという南部のど真ん中で育ったスティーヴは少年の頃から体制や家庭に反抗的だったようで、16歳で高校をドロップアウトして、当時彼が憧れていた伝説のカントリー・シンガーソング・ライター、タウンズ・ヴァン・ザントを追ってミュージシャンの世界に飛び込みました。
1970年代にナッシュヴィルに移り、ソングライターとしてのキャリアを開始、80年代に入る頃にはジョニー・リーやコニー・スミスといったベテラン・カントリー・ミュージシャンが彼の曲を取り上げてヒットさせるに至り、彼の名前がシーンで少しずつ浸透。1986年にメジャー・レーベルのMCA(現ユニヴァーサル)と契約、リリースしたのが今回ご紹介する『Guitar Town』です。
このアルバムは当時大きな評価を持って迎えられ、スティーヴはハンク・ウィリアムスやウェイロン・ジェニングス、タウンズ・ヴァン・ザントといった伝統的カントリーの巨人たちのみならず、ブルース・スプリングスティーンやジョン・メレンキャンプといった70~80年代を彩った硬派アメリカン・ロック・アーティスト達の影響も強く感じられる、いわばネオ・カントリー・ロックの旗手として鮮烈なデビューを飾ったのです。
このアルバムは当時としてはカントリー界ではまだ珍しかった、三菱X-800というDAT(デジタル・オーディオ・テープ)を全面的に使ったデジタル録音だった、というのも新しいネオ・カントリーの時代を象徴する事実でしたし、彼はこのアルバムでこの年の第29回グラミー賞では最優秀男性カントリー・ボーカル部門と最優秀カントリー・ソング部門にノミネートされるなど、一気にその存在をシーンで確立しました。
そんな状況でリリースされたこのアルバム、全編を通じてまだ若いスティーヴ(当時まだ31歳!)が意欲とエネルギーを存分に自ら書いた楽曲の演奏に満ちあふれている、聴くごとに元気の出るアルバムです。
アルバム冒頭のタイトルナンバー「Guitar Town」は当時第2弾シングルとしてリリース、彼の初のカントリーチャートトップ10ヒット(最高位7位)となったスティーヴ初期の代表曲。骨太のギターのリフをバックにウェイロン・ジェニングスあたりを彷彿するような伝統的カントリー・スタイルのミディアム・ナンバーですが、伝わってくるグルーヴは既にロックンロールのそれです。
続く「Goodbye’s All We’ve Got Left」はブルース・スプリングスティーンの初期のナンバーを思わせるようなミディアム・テンポのロック・ナンバー。この2曲は大変強力で、アルバム始まってこの2曲を聴くと、この手の音楽好きの方であれば一気にハマってしまうこと請け合いですね。この曲もシングルカットされ、同じくカントリー・トップ10ヒット(最高位8位)になりました。
同じくカントリー・チャートで小ヒットとなった「Hillbilly Highway」はアコギとウッドベースだけでシンプルに歌われるウォーキング・リズムのヒルビリー・スタイルの曲。このようにカントリーの伝統的なスタイルとロックンロールのスピリット満点のスタイルを交互に、あるいは曲によっては渾然一体と聴かせるというのが、今までを通じて一貫したスティーヴのスタイルで、彼の作品の魅力の最たるところです。
そして今度はジョン・メレンキャンプの曲をハンク・ウィリアムスが歌ってるかのような、ハートランド・ロック調の「Good Ol’ Boy (Gettin’ Tough)」、シンプルなアコギだけの弾き語りでスティーヴのボーカルの魅力が炸裂する「My Old Friend The Blues」と続いてアルバムA面が終わります。
アルバムB面は、一瞬イントロがイーグルス初期を連想させてくれますが、スティーヴのボーカルとエレキギターのリフが入ると一瞬に彼のカントリー・ロックの世界に突入する「Someday」でスタート。ラウンジ・ギター風のリフがネオ・ロカビリーで2:15という短さが潔い「Think It Over」(そういえばこの1986年という年は当時のネオ・ロカビリーの旗手、ドワイト・ヨーカムのデビューの年でもありました)から、このアルバムでは一番カントリー・ポップっぽいイントロとアレンジで、おそらく当時カントリーだけでなくメインストリームのエアプレイも狙ったと思われる、それでもスティーヴっぽいゆったりとした佳曲「Fearless Heart」とB面は少し落ち着いた感じのトーンで進みます。
「Little Rock ‘N’ Roller」は、アーカンソーのトラック・デポで見かけた少年をロックンローラーに模して「君のパパはまたしばらく帰って来ないけど、心配しなくていいよ/おやすみ、チビのロックンローラー/君も大きくなったらバスに乗って出かけて、全てはオーケー/それまではママと一緒にいるんだ」と父と子の関係を思わせるような静かな曲。他の曲の歌詞がこの頃はまだ普通のカントリー系楽曲のテーマ(男同士のつきあいの楽しさ、こんな街は出て行ってビッグになるんだ、失った恋に対する後悔、などなどお馴染みのテーマです)がほとんどの中で、この曲だけはちょっと異色な感じがします。
そしてアルバムはまた伝統的カントリー・スタイルに戻って「これまでも長い道のりを来たけど/まだまだ先は長い/どうしたら愛に巡り会えるんだろう/それがここになければこの道の先にあるに違いない/ただそれを求めて進み続けるだけ」という、スティーヴが本格的にキャリアに乗り出そうという決意を感じる「Down The Road」で静かに完結します。
この頃スティーヴはおそらく自分の前途は可能性に満ちていたし、希望で一杯だったろうと思われます。この時点で既に彼は三回の結婚・離婚を経験し(笑)、ちょうど2000年代後半から才能に溢れたオルタナ・カントリーのシンガーソングライターとして活躍している息子のジャスティン・タウンズ・アール(タウンズというミドルネームはもちろんスティーヴのアイドル、タウンズ・ヴァン・ザント由来です)が生まれて間もない頃で、プライベートでも充実した時期だったと思われるので、このアルバムのポジティヴなパワーとこの先を見つめる意欲に満ちた雰囲気は非常によく判ります。
ただこの後スティーヴは1987年に2枚目『Exit 0』、1989年には彼の初期の傑作と言われる3枚目『Copperhead Road』、そして4枚目『The Hard Way』(1990)をリリース後、90年代前半はドラッグ依存のためまったく活動を停止、MCAからも契約更新を断られることに。この時期彼はヘロインやコカインの不法所持、そして銃器不法所持で60日間の拘留をくらうなど、プライベートでは最低の時期だったようです。
しかしその後90年代後半から活動を再開、インディーからリリースしたフォーク・アルバム『Train A Comin’』(1995)は商業的には成功しなかったものの第38回グラミー賞では最優秀コンテンポラリー・フォーク・アルバム部門にノミネートされるなど次第にシーンへの復活を果たし始めます。
自らのレーベル、E-Squareレコードを立上げてリリースした『I Feel Alright』(1996)を皮切りにここから2000年代にかけては彼の第2期の充実した活動時期に。個人的にこの時期の傑作だと思う『Transcendental Blues』(2000)や、9-11同時多発テロ以降急速に右傾化するアメリカを憂えて反戦、そして死刑制度に反対するという思いテーマに満ちた名盤『Jerusalem』(2002)など政治的なスタンスを明確にした(彼は前回の大統領選でもバーニー・サンダースを支持するなど、社会主義派リベラリストを自認しています)作品をリリースする一方、自らのアイドルへのトリビュートアルバム『Townes』(2009)をリリースするなど、音楽活動の絶頂期。一方、2005年には、カントリー・シンガーであのシェルビー・リンの妹としても知られるアリソン・ムーラーと7回目で今のところ最後の結婚(笑)をし、息子のジャスティンも4枚目のアルバム『Harlem River Blues』(2010)で見事メジャーシーンブレイクを果たすなど、プライベートでも最高の時期だったのです。
アリソンとは2014年に離婚してしまいましたが、その後もスティーヴは、T-ボーン・バーネットをプロデューサーに迎え、ハンク・ウィリアムスの曲のタイトルから取った『I’ll Never Get Out Of This World Alive』(2011)と同タイトルの小説を上梓、拘留中に直接激励のメッセージを送ってくれたという彼のヒーローの一人、故ウェイロン・ジェニングスに捧げたハードコアなカントリー・アルバム『So You Wanna Be An Outlaw』(2017)、そして駆け出しの頃にバンドメンバーとしてメンターの一人として仰いでいた故ガイ・クラークへのトリビュート・アルバム『GUY』(2019) など、気骨とミュージシャンシップに溢れたアルバムをコンスタントにリリースし続け、今でもオルタナ・カントリー/アメリカーナのシーンで中堅・若手のアーティスト達のインスピレーション的存在として活躍を続けています。
この『Guitar Town』の若々しくセクシーな風貌から、今は毛もなく(笑)体型も二回りほど大きくなり、髭伸ばし放題と全くイメージが変貌してしまったスティーヴですが、彼の体には熱いミュージシャンとしての血が未だに脈々と流れている、そんな心動かされる彼のレコード。
熱い夏だからこそ、従来からの彼のファンであれば今一度彼の原点でもあるこのアルバムに耳を傾けて、彼の音楽への感動を新たにし、彼の名前を初めて聞いた洋楽ファンの方には、こんな熱いアーティストがいるんだ、というを是非知って、そして彼の音楽を楽しんでみてはいかがでしょうか。
<チャートデータ>
ビルボード誌全米アルバム・チャート 最高位89位(1986.11.15-22付)
同全米カントリー・アルバム・チャート 最高位1位(1986.11.8付)